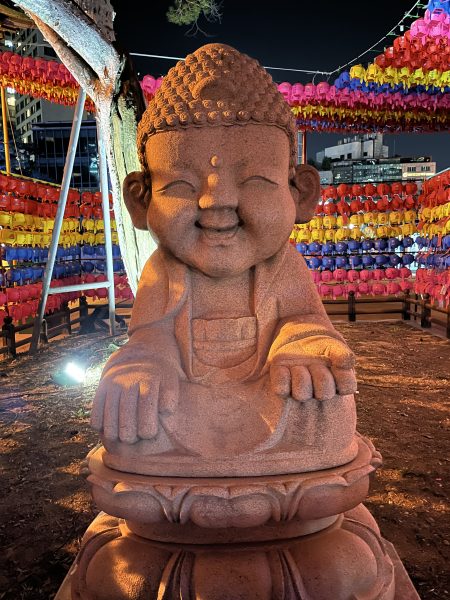"Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away." 「完璧さは、加えるものがなくなったときではなく削るものがなくなったときにあらわれる」 (「星の王子様」著者、サン=テグジュベリ) 総合格闘技のレベルがどんどん上がって...
Read More2025年1月、太気拳気功会40周年記念演武会が開催されました。 (気功会師範の島田先生は私の師、当武禅会は気功会松井道場としてスタートし、その後島田先生に武禅会として開いて頂きました。) 太気会天野敏先生、中道会鹿志村英雄先生に加え、東京オリンピックで日本レスリングチームの監督を務められた西口茂樹先生がご来賓として列席されました。 先生方の演武と道場生の組手もあり、厳かな中にも楽し...
Read More不動心とは 不動心とは石のように「動かない心」ではなく「とらわれなく自在に動く心」です。 そして立禅は不動心を得る修練でもあります。 (太気拳においては精神的な面よりも、物理、神経面に焦点を合わせることが主体です。ただ、ここは明確な分別はできません。) 動くのになぜ不動か 不動心とは「今」を基準にしたとき、「不動」ということです。 「今」は刻々と変化しています。 その「今」の...
Read More