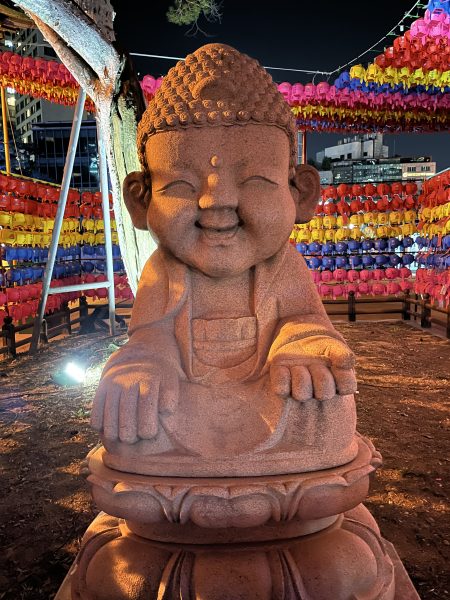「弾力のある身体」の三原則②「骨を徹る力」
April 17th, 2025
ひとつめの原則「もたれてもたれず」によって体重を力に変換することができた。
そこで原則②、「骨を徹る力」だ。
この原則によって、体重=力を筋力に頼らず効率的に相手に伝達するルートを作ることができる。
これが分かりやすいのは割り箸を使った実験だ。
この実験は太気会の天野敏先生から受けたものをそのままパクっている。
というか私の武術は全て我が師、島田道男先生や多くの先生からのパクリである。
だが誰かにそれをお伝えするときには自分の身体と言葉で蒸留できたものだけにしたい。
割り箸を半分を折る。
完全に折らず、木の繊維でかろうじてつながっているようにする。
その一端を持ち、反対の先端で何かをいろんな角度で押してみよう。
するとほとんどの角度では折れた部分が動いてしまう。
だがいまにも折れそうな割り箸でも、ある角度では力を伝達することができるのだ。
これが人間の骨格にもあてはまる。
フックなど肘を特定の角度に曲げて力を加える動作には、肘を曲げて保持するために上腕二頭筋や上腕三頭筋などに力を入れる必要があると思われるが、適切な関節の角度を保つことができれば筋力はほとんど必要ないのだ。
これが「骨を徹る力」だ。
先ほどから「骨」と打つたびにMacBookがを使え、としきりに変換候補に挙げてくるので仕方がないので使ってみよう。
☠️☠️☠️☠️☠️
どうだろうか。ただ読みにくくなっただけだ。
「骨を徹る力」がイメージしづらいという場合は、腕を真っ直ぐに伸ばして壁を押せばいい。
このとき、体重を壁に伝えるのに腕はそれほど辛くないはずだ。
だが、関節をまっすぐに伸ばした構造では動きに変化をつけることができず動けない。
そんな時は割り箸の実験を思い出して強い構造をつくってみてほしい。
腕にも、足にも、身体全体にこの力が適用されることがわかるはずだ。

嫌なことをされると無表情になる