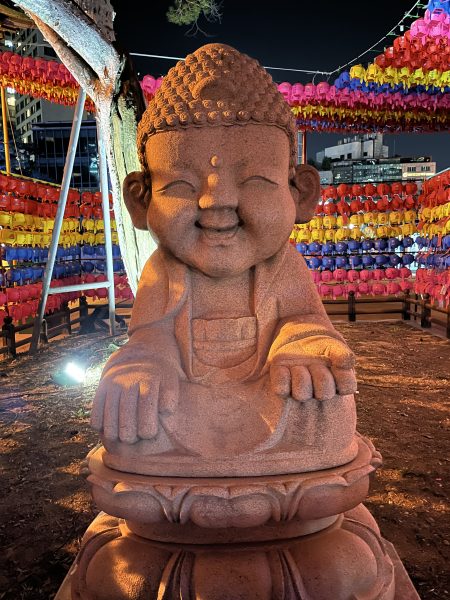相打ち
February 3rd, 2025
打たれたら打つ
相手が打ってきたら守るのではなく、ためらうことなく打ち返す。
相打ちが基本にして極意です。
相打ちを突き詰めていくと、一方的に自分のみが打てるようになります。
そしてお互いが打てず打たずに至り、争いを未然に防ぎます。
なぜ相打ちか
攻撃ではなく身を守ることが武術じゃないの?と思われるかもしれません。
もちろん身を守ることが大切です。守るためにこそ、相打ちが有効となります。
防御してから攻撃、ではなく相打ちを基本とするメリットを3つ挙げます。
1、距離とタイミングが合う
相手が打ってくるということは、その瞬間は自分にとっても相手が届く距離にいるということです。
体格差、リーチ差がある場合も、相手がゾウやキリンでない限り半歩でも動くことができれば必ず届く間合いになります。
距離、角度、タイミング(時間)、心理的作用等を総合した感覚が「間合い」といわれますが、それを掴みやすいのが相打ちです。
2、攻撃の瞬間は防御が甘くなる
人間は2つのことを同時に考えることができません。
打ってくる相手は攻撃のことを考えていますので防御が甘くなります。
もちろん相手はガードをしながら打ってきますが、あくまでも主体は攻撃です。
つまり相手が攻撃してくる瞬間は、こちらにとっても攻撃のチャンスでもあるのです。
3、相手が攻撃をためらうようになる
「来るならやり返すよ!」という心構えでいると、相手は手をだすことをためらうようになります。
殴ったら殴り返してくる人と殴ったら逃げる人、どちらが怖いでしょうか。
自衛隊と同じですね。自分からは攻撃しないけど、やってくるなら受けてたつよ!という気構えが、自分を守ることになります。
相打ちからの変化
相打ちの稽古をはじめたばかりの頃は、
「きた!打ち返さないと!」
と相手の動きを見て動きはじめます。
これは完全に遅いタイミングで、相手の打撃だけが当たってしまいます。
少し慣れてくると、
「くる!」
と相手の動く気配を察知するようになります。
気配を感じたら打つので、実際には相手が動かずに自分だけが一方的に打てることもあります。
(逆に打つフェイントにやられることもあります。)
完全に身についてくると、
「!」
と何も考えずとも身体が勝手に動きます。
ちょうどいい間合いを身をもって得るのが相打ちです。
相打ちの間合いを基準点として、相手が打ってきたところを受けて返す「後の先」、相手の打ち気を制して先に出る「先の先」などバリエーションが生まれます。
そして相打ちの感覚がつかめてくると、そのタイミングで防御もできるようになります。
相手からの攻撃時に相手の顔や胴に向かって相打ちをしていたのを、攻撃してきた腕に向かって手を出したり、体を動かして避けることで防御になるという具合です。
相打ちから不争へ
相打ちが基本にして極意だとすれば相手もまた相打ちを狙います。
お互いが相打ちを研鑽しレベルが上がると、お互いに攻撃したらやられる、という状況になります。
すると戦いは未然に防がれることになります。
格闘技の試合ではこうはなりませんが、お互いがナイフを持った状況を想像するとわかりやすいかもしれません。
そんな時は相手を刺すことよりも自分が刺されないことを優先するのではないでしょうか。
無住心剣という剣術の流派に相抜けという伝承がありこれが目指すところですが、詳細は伝わっていないようです。
国家の核保有の理論にも通じるところがあるかもしれません。
できれば戦いを避けたい、自分よりも強い相手とのやむをえない戦いをなんとか切り抜けるのが武術です。
自分よりも強い相手との戦いで、自分はうまく防御して無傷で生き残ろう、というのがそもそも虫のいい話です。
肉を切らせて骨を断つという捨て身の覚悟があってこそ無傷で生き残る、という可能性が生まれます。

太気拳の組手